法律コラム
微笑みを
明けましておめでとうございます。
今年も宜しくお願い致します。
さて、新年の初めからくだらない話で誠に恐縮なのですが、他に思いつかなかったのでご容赦下さい。
うちの妻は活字好きで、チラシ好きなこともあり、我が家では結婚してからずっと新聞を取っています。私はさほど新聞が好きな訳でもないので朝食の際にパラパラと眺める程度ですが、うちで取っている新聞には今でも「人生案内」の欄があり、そこは結構楽しんで読んでいます。世の中には実に様々な悩みがあるんだなと、いささか唖然とさせられます。中には「ここでそんな相談してる場合か」というものもありますし、「そんなことここに相談してどうするんだ」といったものも散見されます。ただ、何と言っても一番興味深いのは家族間の悩み、ことに夫婦間のそれです。一番身近に感じられるので、最もボリュームを占める相談内容になっています。そうした相談があると、もぐもぐと朝食を頬張りながら「今日はこんな相談が載っているけどさ…」「これってこうじゃないかなぁ…」と妻とたわいもない話をします。それなりに会話が弾みます。ほぼ同意見のことが多いのですが、多くの場合、妻は「私なら、すぐに出て行くけどなぁ」「そんなことでは結婚してても意味ないし」ときっぱりと言っており、その立場ははっきりしています。
また、自分でも何故かよく分からないのですが、私はYoutubeで「熟年離婚に至る…」とか「妻が愛想を尽かす…」いうような動画をチラチラ見ています。そして、「こんなこと言ってたよ」とか「これがマズイんだってさ」といった話をします。すると妻は「また、そんなもの見て」と呆れつつ、やはり「当たり前じゃない!」「そんなことも分からないのかしら」「私なら絶対に我慢しないわ」などときっぱりと言っています。やはり立場はとてもはっきりしており、気を引き締めねばと思わされます。勉強になります。
投書でも動画でも、女性側のものの方がどこかユーモアがあり、内容もビビッドで見ていて面白いです。他方、男性側のものは少し悲壮感が漂っており、独りよがりのものも多く、いささか暗い気持ちにさせられます。読み物としてそもそも勝負になっていない。
話は変わりますが、チャップリンの作ったSmileという素晴らしいスタンダードがあります。歌詞の内容は「つらくても微笑むんだよ(前を向くんだよ)」「そうやって生きていくんだよ」「そうすれば光が差すからね」というものです。生きていると大小様々な試練の連続で、「いい加減にしてくれよ」と言いたくなることもありますが、この曲を聴くと、つらくても前を向いて微笑むように生きていかなくてはなと改めて思わされます。不幸をかこっていて仕方ない。そう、「不幸な者の言うことには、神様だって耳をお貸しにはならない」のだから。
If you smile through your fear and sorrow
(怖れや悲しみに遭っても微笑んでいれば)
Smile and maybe tomorrow
(微笑むこと、そうすれば明日)
You’ll see the sun come shining through for you.
(太陽がまたあなたのために輝くのを見ることになる)
ということで、今回はここまで。
今年も残りわずか
今年も残りわずかとなりました。去年も同じことを書きましたが、「ああ、何とか無事に乗り切ることができた」と内心ホッとしています。毎年、初詣で「今年こそは心穏やかに過ごせますように」と神様にお願いするのですが、これまで上手くいったためしがありません。毎年、何かしらのアクシデントやトラブルに見舞われては、そのことで心を悩ませています。もう勘弁してくれという気持ちです。昔、「40歳で不惑」と教わりましたが、とても無理です。
まあ、そんなことを言っていても話が暗くなるばかりなので、ここでは今年良かったことを書きたいと思います。
まず第1は、とても平凡なことですが、家族が皆大きく心身を損なうことなく、何とが無事に過ごせたということでしょうか。私も交通事故に遭って入院し、人生初めての手術こそしましたが、別に麻痺等が残ることもなく、当たり前に日々を過ごせています。良かった良かった。
第2は、父をきちんと見送ることができたということでしょうか。最後まで父の尊厳を保った状態で、落ち着いて父を見送ることができました。「やるべきことはやった」という気持ちで送れたことが、個人的にはとても嬉しいです。この種の事は取り返しがつかないので。
第3は、これも平凡なことですが、それなりに日常を楽しむことができたということでしょうか。休日に家族で出掛けて美味しいものを食べたり、いろいろと旅行をしたり、いろんな美術展に行ったり、たくさんの音楽を聴いたりして、日々を楽しむことができました。
話は変わりますが、父が亡くなり実家が空き家になってしまったので、暇を見つけてはその整理に通っています。ただ、私の実家は物があふれかえっているので、いささか途方に暮れています。今は父が書斎に使っていた部屋を整理しているのですが、ここもなかなかのものです。ただ、父の書斎でひとり整理をしていると、父の気配を濃厚に感じ、いささか心がしんとします。「ああ、そうだったな」と物思いにふけったり、父に関する様々なことを思い出します。自分との類似点にも気づかされます。また、父の蔵書を見て、私よりも私の息子とすごく興味が似ていることに気づいて、不思議な世代の連鎖を感じたりもします。なかなか悪くない時間です。
そうして過ごしていると、父と母が大人になるまで私を大事に護り育ててくれて社会に送り出してくれたことに改めて気づかされます。それを当たり前のものとして享受できていたことの有り難さが身に染みます。
さて、次は私の番ですね。大変心配ではありますが、ある時点で勇気を持って息子を社会に送り出してやらねばなりません。親に出来ることなんて知れている。あとは痛い目に遭って本人が自分で学ぶしかありません。
というようなことを感じる1年でした。
それでは皆様、良いお年を。
またもや身辺雑記
ここ数ヶ月妻と2人で近隣の県に1泊2日の旅程で出掛けています。今年は父親のことがあったり、自分も入院したりで、恒例の家族旅行が全部キャンセルになってしまったので、その埋め合わせという意味もありますが、単純に楽しいので何度も小旅行に出ています。これまで奈良、三重、和歌山、福井に行きました。
全て自分で運転して行き、その土地の名物を食べて、ゆっくり観光して、できればお風呂に入ってという感じで、この方式の良いところは思い立ったらすぐに行くことができる手軽なところです。手頃な宿さえ押さえられれば(ネット予約できるのでとても便利)、思い立ってすぐ週末にでも出掛けることができます。図書館で旅行本を借りて、主な観光スポットをおさえ、あそこに行ってここに行ってと予定を組みます。ただ、突然行くため息子とはなかなか予定が合いません。彼は基本的に留守番です。でも、その代わりに、息子は妻から「食事代」の名目でお金を貰い、それで自分の好きな物を食べに行っており、なかなか悪くなさそうです。三方良しですね。ただ、もう近場では行くところがなくなってきたので、それが悩みではあります。
今ではコルセットも外れたので、やりたい放題です。まだ腰に金属プレートが入っており、骨を固定しているので、「かがむ」ことがなかなか難しく、靴下をはいたり靴紐を結んだりするのは一苦労ですが、それ以外に特に不自由していることはありません。主治医の許しも出たので、ウォーキングや軽いジョギングも出来るようになりました。おかげで増える一方だった体重も何とか落ち着き、筋肉も付いて体のシルエットも前より少しは整いました。うん、悪くない。
今年は何だか色々と大変なことが重なって個人的に「しんどい」年ではあるのですが(息子も今年はなかなか大変な目に遭っているようで、ブチブチと家で文句を言っています。比較的無事なのは昨年えらい目に遭った妻だけです)、あと1月ちょっとなので、何とか無事に乗り切れればと願っています。
そういえば年始にNHKの「たなくじ」で,今年はすごく良いことが2つあると出たのですが、まだ2つ目が来る気配がありません。どうなっているのだろう。
全く関係ないのですが、先日テレビを見ていたら、えらい寺のお坊さん(貫首クラスの人)が、ある芸術家について「神の領域に入った(大変なことだ)」といった話をしておられました。個人的に凄い違和感でした。おしまい。
考える時間
自宅から車で片道1時間ほどの距離を通勤しています。自分で事務所を開いている弁護士だと、職住近接が普通なので、こんなに時間をかけてわざわざ通勤しているのは珍しいパターンかも知れません。
とはいえ通勤時間もそれなりに役に立っているので、特に不満という訳でもありません。私にとって1時間ほどの通勤のメリットは、(1)CD1枚分聴けるだけの時間が確実に確保できる、(2)考える時間が無理なく確保できる、(3)プライベートと仕事を切り離すことができる、といったところです。
(1)については、自宅では嫌がられる「うるさい」タイプのジャズをそれなりの音量で聴くことができますし、自宅のステレオ・セットで聴くよりも車で聴く方が心に響く音楽もあったりするので、なかなか有意義です。ロードノイズのため、小さな音や特定の周波数帯の音(特に低域)が聞こえにくいため、聴く音楽の種類が限られるという難点はありますが(高級車に乗れば違うんでしょうか)。
(2)については、仕事やプライベートについて、つらつらと考えることができてとても重宝しています。難しい事件など、あれやこれや考えているうちに考えもまとまるので、とても貴重な時間です。私の場合、机の前でさあ考えようと思っても、なかなか集中できない性格ですので。
考える時間ということでいうと、一人で外でお風呂に入っている時間もなかなか貴重です。露天風呂に浸かって、あるいは、浴槽の縁に腰掛けてボ-ッと空でも見ていると、その時々に頭を悩ませていること、人生のあれやこれやが頭に浮かんでは消えていきます。その多くは他者に対するものではなくて自分に対するものです。いささかうんざりした気持ちになったりもします。でも、そうしていると、少しずつ気持ちが整理されてきて、何となく色んな物事が自分の中であるべきところに納まっていきます。「まあ、そんなところだろ」「文句言える立場じゃないよなぁ」いった気持ちになってきます。考えたり気持ちを整理するのに時間がかかるのが難点ですが。
それにしても、平凡な人生でも実に様々なことが起こりますね。思いもしないことが待ち受けています。
Everything Happens To Me
Matt Dennisの歌うとおりですね。
お叱りを受けるかも知れませんが
弁護士をしていると、何とも対応困難な場面にちょくちょく出くわします。
その理由のひとつに「立証」の問題があります。例えば「○○である場合には△△とする」と法的に規定されており、それ自体は誰の目から見ても是認できるものであるとします。ただ、問題は、それ(法律要件たる「○○であること」)を立証できるかという問題にあります。それが困難極まりない場合がちょくちょく発生するのです。その結果、立証ができないからという理由で、望んだ結果(法律効果)を得られないということになってしまいます。真実を知る当事者にとっては、耐えがたいことです。嘘をついている人が得をしていると感じるからです。
また、道徳的な価値判断と法的な価値判断が必ずしも一致しないことも難しい問題を生じさせます。結果として「悪いことをしておいて、賠償しなくて済むのか」といったフラストレーションを生むからです。道徳的観点から「非」という評価を受けるもののうち、特に悪質な一部だけ取り出して、法的に「非(違法)」との評価を与えて規制しているためであり、それ自体は決して理由のないことではありません。歴史的な理由もあって、現在の日本では、法が道徳に必要以上に深く介入すること(特定の道徳観を強要すること)を嫌うのです。ただ、当事者さんに大きなフラストレーションとなることは、立証の問題と同様です。
そうした事態に直面すると、我々も対応に窮します。ただ、立場上、無理なものは無理だと伝えざるを得ません。経験上、そこで躊躇しても良い結果を生みません。
そんな時、私は、よく「あんなことをしていると、その報いを人生の中できっと受けることになりますよ」といったお話しをします。別に単なる慰めでそのように申し上げているつもりはなく、そう感じているから、率直にそう申し上げているに過ぎません。どう生きるかということによって、その人生は規定されていく、貧しい生き方をしていると、人生はそのようにして限定されていくと私は感じます。ご本人が自覚するしない(痛みを感じる感じない)とは無縁の、自分自身にも当てはまる避けがたい問題として。そう考えると、「人生の収支はバランスしている」し、目先の、ある意味では技術的な理由でもたらされる不本意な結果に拘泥するのも、「何だかなぁ」という気にならなくもありません。それで上記のように申し上げるわけです。理屈の問題として。
ただ、そう申し上げても、「まあ、本当にそうならいいんですけどね(期待できませんね)」「やれやれ」といった様子をされる方がやはり多数です。当然ですね。人々が我々に求めているのは、自らの要求の現実的な充足であり、法的な勝利です。人生論じみた理屈で当面の問題は解決しないし、とても納得できるものではありません。
では、一体どうすれば良いのか?
途方に暮れてしまいます。
God Only Knows
そういえば、先日、Brian Wilsonが亡くなりましたね。合掌。
激動の1月
先月コラムをアップしてからの1月間は、まさに激動の1月でした。
というのも、自転車に乗っていて自動車事故に巻き込まれてしまい、人生で初めて骨折し、入院生活を送ることになったからです。結構シリアスな事故で、全身麻酔で手術をすることになり、今でもコルセット生活です。一生懸命リハビリしたので、今では普通に歩くこともでき、「ごく普通」に生活できるまで回復しました。ただ、もうちょっとで(もし骨折の部位が少しズレていたら、もし骨折の方向が少しズレていたら)麻痺が残って車椅子生活になるところでした。看護師さんには「こんな風に骨折してたんですよ(と色々と身振りを交えて教えてくれる)。普通はすぐに手術ですし、ヘタしたら麻痺でしたね。よくこの程度で済みましたね」と驚かれましたし、理学療法士さんには「よくそんなに歩けますね。でも、命まで取られなくて本当に良かったですね」と慰められました。担当の警察官にまで「この怪我だと、私の経験からいってかなりヤバイです。正直、麻痺になるかと思ってました」と驚かれました。夏の暑い盛りにコルセットはいささか拷問ですが、その程度で済んだことに感謝です。とても贅沢は言えません。
入院生活を送って一番痛切に感じたのは、馬鹿みたいではありますが「暇で困る」ということでした。日がな一日やることもなくベットの上でボーッとして、喰っちゃ寝、喰っちゃ寝して、時間つぶしに読書したり、ゲームしたり、うたた寝したりしていると、「こんなことしてていいのか?」といささか頼りない気持ちになりました。
初めて入院生活を送り、医療関係者の仕事がどれくらい大変か実感しましたし(一体どんだけ働くんだ)、仕事って結局は人間性だよなということも改めて感じました。私の主治医(整形外科)のM先生は若い男性で、かなり年下ですが、元気に前向きに話をしてくれますし、こちらが質問すると逃げずにリスクも含めて正面から返事してくれましたので、私としては、とても好感が持てましたし、信頼感を持つことができました。同じ専門職として学ぶべき点が多かった。看護師さんも娘みたいな年頃の方が多かったですが(「川瀬さんて、うちのお母さんと同年代なんですよ~」と話しかけられ、色々と感慨深いものがありました)、とても親切で前向きで、やり取りしていて気持ちが良かったですし、何より気持ちが明るくなりました。自分が同じくらいの年の時には、自分のことで精一杯で、とてもあんな風に他者に接することなどできませんでした。すごい。何でそんなことできるんだ?
これからしばらくはコルセット生活ですし、1年ちょっとしたら再手術とも言われているので、長丁場になりそうです。ただ、「運良く」この程度で済んだので、そのことに感謝し、これまで通り、あまり肩肘張らず自然体で生活していきたいと考えています。
ただ、入院して高血圧が判明し、薬を飲んで毎日血圧を図る生活になってしまったことには正直閉口しています。これまでは週に2回の休肝日を守って正常値を誇ってきたのに何故だ! お酒もラーメンも明太子も好きなんだよなぁ。嫌だなぁ。困ったなぁ。
といった感じの1月でした。
生の音楽は良いですね
今月は珍しいことに、立て続けに2回音楽をライブで聴く機会がありました。
1つは、美術展を見るために訪れたさる大学の施設で偶然出会ったヴァイオリン四重奏のロビーコンサートでした。どうも卒業生(あるいは在校生)の若い4人組のようで、緊張しながら仲間と合図を送り合って一生懸命合奏しており、とても好感が持てました。技術もしっかりしていて、演奏も楽しめました。ちょうど息子くらいの年代だったこともあって、親しみの持てる良いコンサートになりました。
もうひとつは、びわ湖ホールで行われたプロのコンサートでした。ジャズ・ピアニスト山中千尋さんのピアノトリオでしたが、この日もすさまじい演奏で、ほぼ同い年なのにと吃驚されられ通しでした。ただ、私がこの日一番驚いたのは何と言ってもドラマーで、このドラマーがまたすさまじく、山中さんに全く力負けしていないばかりか、場合によっては山中さんを喰ってしまおうという勢いでした。高い技術に裏打ちされた、スピード感のあるダイナミックな演奏で、ものすごいグルーヴでした。ピアノとドラムとが、すごいスピードで急流下りのように複雑なソロを同時にとっていき、どこまでも高め合って登りつめていく有様は、まさに鳥肌もので、ジャズを聞く醍醐味を味わわせてもらいました。
こうしてある意味では対照的な2つの音楽体験をしたわけですが、そのどちらも音楽を聴く喜びを存分に味わわせてくれるものでした。デジタル・データが全盛で、定額制音楽配信が一般的ではありますが、やはりこうして生の音楽に触れると、「音楽を聴く喜び」を鮮烈に味わうことができます。生には生の良さがあり、録音物では代替のきかない喜びがあります。それは私個人にとって、とても意味のあることです。
ただ、そのために「ドーム」や「アリーナ」みたいな場所にまで出向きたいとは正直なかなか思えません。行き帰りのことを考えるだけでゲンナリしますし、そもそも音楽がちゃんと聞こえるかかなり怪しそうです。ひとつの体験としては楽しいと思うのですが、そこまでの熱意が出てこない。妻には誠に申し訳ないのですが。
あれれ、ネガティブの内容で終わってしまった。
おかしいな。
大学院だと…
息子は現在3回生なのですが、先日、大学院(修士課程)に進学したいと相談されました。
私は世代も違いますし、文系(法学部)だったこともあって、今でもピンときませんが、息子の話では、最近は理系では大学院に進学するのはごく普通のことのようです。
正直「浪人しておいて、まだ2年も余計に行くのかよ」「いい加減、社会に出たらどうだ」とも思いましたが、勉強がしたいから進学したいという前向きな話でしたし、人生で学問に打ち込む期間があってもよかろうかと思い、許すことにしました。自分も司法試験浪人を2年していて「脛に傷持つ身」でもありますし。
ただ、原則として修士までだと釘を刺し、親としてお金を出すのは「学費だけ」で、あとは奨学金を借りるなり何なりして自分で工面するよう伝えました。自分の希望(趣味)であえて進学するのだから、その程度の負担は当然自分ですべきだと思いましたし、身銭を切る覚悟がないのなら、本物とは言えないと思ったからです。息子は当然のこととして、それを受け容れました。
などと今では偉そうなことを言っていますが、自分が同じ年頃だった時のことを思うと、忸怩たるものがあります。その頃の私は、未熟で、不完全で、世間知らずで、司法試験になかなか受からず、実家で悶々とした日々を過ごしていました。皆社会に出て立派になっていくのに、俺は一体何をしているんだろうと情けない思いをしていました。冬のまだ夜明け前、こたつに入って横になり、自分の前途について考えては絶望的な気分になっていたことを思い出します。そのために彼女(今の妻)も待たせてしまっていました。
それに比べると、息子は何と立派なことか。
全て知っている妻は「そんな偉そうなこと言っちゃってさ」といった目で、横から私を見ていました。言うまでもないですが、妻は息子の味方です。
でもさ、言わなきゃ仕方ないじゃないか。
立場上さ。
柄にもない話ですが。
ジャズの古いスタンダード・ナンバーにIt`s Only A Paper Moonという有名な曲があります。私は、Miles Davisのキャリア初期のアルバムDigでその曲を知りました。そこでのMilesの演奏は、とても親密でスイートです。ボーカル入りであれば、Nat King Coleの弾き語りがお勧めです。とても素敵な曲であり、演奏です。
歌詞は、端的に言うなら「作り物であっても、あなたが私を信じてくれるなら、それは作り物でなくなる(本物になる)」というものです。人が人を愛することの力(奇跡)を歌った典型的なラブ・ソングになっています。
村上春樹は、その歌詞を一部引用する形で、「1Q84」という長編小説を書いています。これも、とても力強い内容を持つラブ・ストーリーになっています。そこでは抗いようのない境遇にある不幸な少女が、ただ一人自分を助けてくれた男の子のことを、ずっと強く思い続ける様子が、とても綿密に描かれます。少女は、ただ一度だけ男の子と二人きりになるチャンスに恵まれ、男の子に駆け寄って、強くその手を握り、じっとその目を見つめます。その時点での自分を全て差し出し、その思いを伝えようとします。その悲壮なまでの決意には言葉を失わせるものがあります。その後別々の道を歩みつつも、少女はその男の子のことを、終生強く愛し続けます。その力が様々な困難を克服する原動力となって、物語は複雑な様相を呈しつつ進んでいきます。この本を読むと、人が人を強く求めるということの素晴らしさにもう一度気づかされます。それが時に強い憎しみを生むものに変わることがあったとしてもです。
優れた物語を読むと、自分のつまらない考え方に気づかされます。同時に偏狭で歪んだ考え方に捕まってしまわないようにというメッセージも受け取ります。
But It Wouldn`t Be Make-Believe (でも、それは作り物ではなくなる)
If You Believe In Me (あなたが私を信じてくれるなら)
お疲れ様でした
今月は余りにも色々なことがあり、何だか気ぜわしくて落ち着いてものを考えられなくなっています。そのため、何を書いたら良いのか途方に暮れています。でも、月に1本は書くと自分で決めたので、何とか書きたいと思います。
印象に残る出来事として、先月下旬、京都のとあるレコード店が閉店しました。そこは40数年続けてこられた老舗で、途中、コロナ禍で場所を移転し、規模を縮小して続けてこられた店でした。京都のレコード文化を守るという気持ちから、年配になられてからクラウドファンディングをしたりして、頑張っておられました。多くのレコード好きが、その姿勢に心を打たれて通っていたようでした。私も微力ながら買い支えないとと思って、せっせと通っていました。ただ、最近は商品が薄くなってしまっており、ちょっと心配していました。そうしたところ、お店を閉められるというSNSを見つけ、慌てて閉店数日前に店にうかがいました。そして、会計の際に、初めて「お店閉められるんですね」「長い間お世話になりました」とお声がけしました。すると、店主の方(おじいちゃん)は驚かれた様子で、「ここまでやるのが精一杯でした」という趣旨のお話しをされ、「こちらこそ長い間お世話になりました」とおっしゃいました。それで不思議と気持ちが少し楽になりました。
形あるものはいつか無くなってしまうし、物事には必ず終わりがある。私に言えることはただ「お疲れ様でした」ということくらいです。
そして、こちらも最後に「お疲れ様でした」と言ってもらえるよう懸命に生きるしかない、そんなことを感じた3月から4月にかけての時期でした。生きていると色々ありますね。
短いですが今月はこれでおしまい。ちゃん。ちゃん。
 東近江で離婚・相続・賠償・借金の法律相談なら
東近江で離婚・相続・賠償・借金の法律相談なら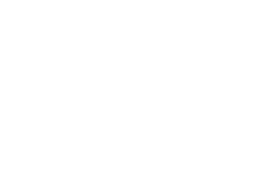 ご予約・お問い合わせ
ご予約・お問い合わせ